2025年10月号 特集 谷川俊太郎 新川和江の仕事
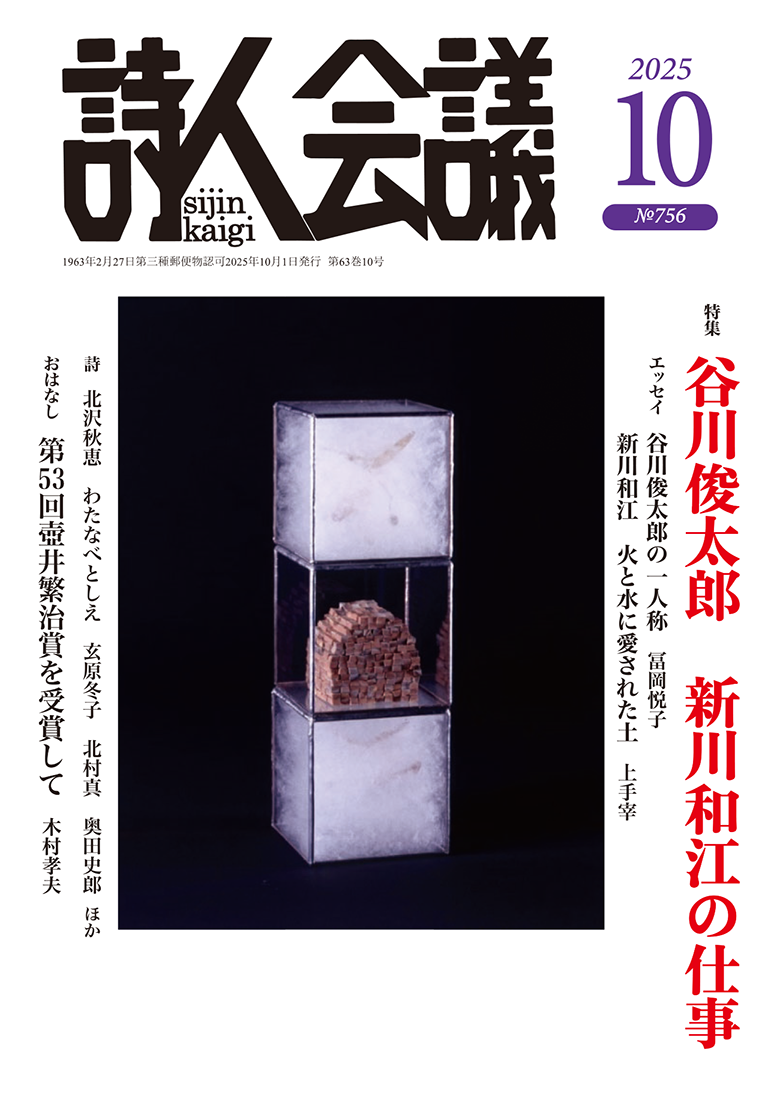
特集 谷川俊太郎 新川和江の仕事
エッセイ 谷川俊太郎の一人称について 冨岡悦子
火と水に愛された土――新川和江について 上手宰
一般詩作品
北沢秋恵 陽炎
わたなべとしえ 書いておきたい詩
玄原冬子 鼓笛隊
北村真 ユウレイ
大杉真 野川にて
田辺修 生きている時間
佐藤一秋 詩作
呉屋比呂志 ヤノ巡査
妹背たかし 快気祝い
坂田敬子 暮れ
三村あきら 落葉松の風
春街七草 731部隊とマルタ
小林信次 あなたは
いいむらすず どこで眠るか
上野崇之 この道はいつか来た道
青木みつお 風車について
三田麻里 口づけ
奥田史郎 以後 お見知りおきを
いだ・むつつぎ 若いメスの蚊たちとじいさん
関口隆雄 梅の花
永冨衛 お世話になります
畑中暁来雄 七夕に泣く
池島洋 沫
高嶋英夫 少年と君が代
いわじろう 自分のためだけに
古野兼 六十年安保の宝物
山﨑芳美 歌と共に
小田凉子 学び
木村孝夫 師走
第53回壺井繁治賞受賞をして
中間貯蔵施設県外移転「2045年3月問題」 木村孝夫
エッセイ アフリカを考える 秋野かよ子
報告 原水禁世界大会・広島 坂田トヨ子
書評
南浜伊作 原圭治著『詩人会議と共に歩んだ浅尾忠男』
宇宿一成 後藤光治詩集『抒情詩篇』
柴田三吉 徐京植『私のアメリカ人文紀行』
見る・聞く・歩く 水崎野里子
ひうちいし 國森伸 山田よう 床嶋まちこ 横田重明 河野俊一
古道正夫小詩集 〈連作〉 森の中
エミリ・ディキンスンの詩を読む⑨ 創作とキッチン 魚津かずこ
詩作案内 わたしの好きな詩 近藤益雄 大木武則
私の推す一篇
詩作入門 百姓の呟き 湯浅きいち
現代詩時評 新聞記事と詩人会議8月号 宇宿一成
詩 集 評 図鑑を片手に・知る歓び あらきひかる
詩 誌 評 夢想ではない、詩的現実。 白石小瓶
グループ詩誌評 故障なんて 脱皮する 春の風の中で 河合政信
自由のひろば (選・横山ゆみ/渋谷卓男/中村明美)
三明十種/森林みどり/石川順一/大今滝路/谷口律子/橋本敦士/
おくむらじゅん/サイキシオリ/大木武則
全国詩誌作品集お誘い
寄贈詩誌詩書
詩人会議通信
●表紙/扉カット/表紙のことば 中島和弘
編集手帳
----------------------
●詩作品
陽炎
北沢秋恵
これから書かれる詩のために
空白を残しておいた
白いノートの一ページより
少し広い脳内
涼しい打ち水をして
静かに待った
というのは私の空想に過ぎない
猛暑である
ゆらゆら陽炎の昇る道を
日傘をぎゅっと握り
郵便局に向かう
二つ三つの用事を済ませるための外出が
荒地を辿る人の歩行めいて
心許なく くらり
郵便局までの道は歩くほど伸びて
どこまでも遠い
街中にさらさらと音を立てていた小川は
干上がってしまったのだろうか
ひび割れて蛇行する
乗客のいないバスが砂埃を上げて
私を追い越していく
現実の方が作り物のようではないか
------------------
●書評 柴田三吉
徐京植『私のアメリカ人文紀行』
憂いに心ふさぐ巡礼の道
二人の兄、徐勝氏と徐俊植氏を全斗煥独裁政権下で拘束されていた徐京植氏は一九八六年に渡米し、人権団体、国務省人権局等で韓国の過酷な思想弾圧の実態を訴えた。これはその日々に記した「旅日記」を軸に、三十年後、夫人を伴った再度の旅と、現在の世界情勢を織り込んだ思索の書である。
韓国の民主化が見通せないなか、当時三十五歳の徐氏は諸都市を訪れて講演し、政権の人権弾圧を糾弾した。悲痛な思いを抱えたその旅を氏は「憂いに心ふさぐ巡礼の道」だったと書く。語学力が十分でなかったゆえのストレス、過密な日程もその一因だった。
だが旅の途上で出会った人権団体のスタッフ、韓国からの移住者たちによる献身的な援助と交流は氏を励まし、厳しい旅への意欲を回復させてくれたのだった。そうしたなか、氏はスケジュールの合間を縫って、訪れた都市の美術館に足を運んでいる。
「(韓国では)決死的な反独裁闘争が続いている時期である。兄たちは獄中で呻吟している。そんな時に、これが良い振る舞いだったかどうか、私自身にもわからない」
と自問しつつも、美術評論家である氏にとって、その巡礼は精神の核を耕すための必然的な行為だった。
メキシコ壁画の巨匠ディエゴ・リベラ、「ラッキー・ドラゴン(福竜丸)」シリーズのベン・シャーン等、感銘を受けた作家、作品への賛辞とともに多くの図版が添えられている。
本書のタイトルに記された「人文紀行」とは、人間が生み出した文化(善き人間性と芸術)と、それに対する反人文主義(不寛容と暴力)を検討する意である。文化を蔑ろにする反知性主義は現在のアメリカを覆っている病であるばかりか、血を流し続ける世界の病でもある。そうした危機を氏は、パレスチナ出身の思想家、エドワード・サイードを偲びつつ語るが、これらの章は哲学的な深みがあり圧巻だ。
*徐京植氏は本書の終章を脱稿した翌日に急逝。生前は私たち詩人会議にも惜しみなく力を貸していただきました。その死を悼みつつ、氏が遺してくれた「善き人、善きものとの出会い」を心に刻んで継承していきたい。
(みすず書房 二八〇〇円)
--------------------
●編集手帳
☆新川和江氏は’24年8月、谷川俊太郎氏は同年11月に逝去。ともに95歳と92歳という長寿を全うして多彩な仕事を成し遂げ、日本の詩に大きな足跡を残しました。そうした多面的な仕事の全貌を俯瞰し、吟味するには多くの時間を要するでしょう。今後の研究が待たれるところですが、本誌はその先駆けとして、冨岡悦子氏と上手宰氏にそれぞれの論考を執筆していただきました。
☆冨岡氏は谷川俊太郎の「僕」から「私」へと移行していく一人称の意味を巡って、上手氏は新川和江の「オード」シリーズに見られる土や火の関りを巡って論を展開。どちらも新鮮な視点で、両者の詩の特質を示しています。引用された作品とともにお楽しみください。
☆詩の豊かさに触れながら、巷で跋扈しているフェイク的言辞がまかり通っている現状に怒りと悲しみを覚えます。政治家から市民まで、公然と嘘を発信しているところに言葉の危機を見ます。それらが政治の方向を過ち、市民を傷つけ、命さえ奪っているのです。(柴田三吉)